国山脈の良質な砂鉄と豊富な木材、そして斐伊川の豊富な水がそれを支えたのである。昼夜寒暖の差が激しい中山間地(標高
200〜700m)で、木材が切り出された跡地はソバ栽培(焼畑)に格好の地でもあった。時は流れ、たたら製鉄は高炉の近代製鉄
に席を譲り、在来ソバはより多収な他府県産(信州・常陸)に駆逐されていった。「横田小ソバ」の再生の取り組み始まったのは
平成15年の「ソバによる町興しプロジェクト」からであった。県農業技術センターに残っていた僅か1kgの在来種ソバ種から数年
かけて栽培・選抜をくり返し現在ようやく栽培面積が9haを占めるにまで至った。毎年11月「奥出雲そば祭り」が開催されている。


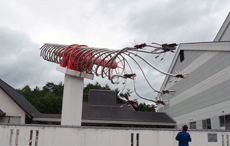

と共に奥出雲を代表的する蕎麦屋。信濃
大そばや常陸秋そばの進出で絶滅の危
機を迎えたが、官民挙げての町興し運動
に押されて「横田小そば」が蘇った。
そば硬くてやや太め。下段:「たたらと
刀剣館」の前に建つ。ヤマタノオロチ
を現した造形。ヤマタノオロチの尾か
ら太刀(くさなぎの剣)がでてきた。
器」で一躍有名になった)は民間委託駅
で、蕎麦屋の主人が事実上駅長を兼ね
る。一日上下併せて10本程度の列車が
通過する。全国からそばファンが来る。
本土との往来も盛んであった。また隠岐は沖縄に次ぐ長寿の島として有名で、長寿博士・近藤正二著「日本の長寿村・短命村」
に詳しい。野菜・海草・大豆・雑穀を常食とし、そばも昔から家庭で打たれていたと伝えられる。島根県の頓原遺跡(BC7〜8世紀)
ではソバ花粉が、タテチョウ遺跡(弥生時代)からはソバの種が発見されている。朝鮮半島→隠岐→山陰地方で直接伝播したと
も考えられる。全国でも珍しいそば打ち踊り(そば打ちの手順)「どっさり節」が隠岐民謡として残っている。隣の石見の国には「三
瓶そば」がある。三瓶山(1126m・大山火山帯)からの火山灰を養分にして育ち、小粒だが粘りの強いのが特長といわれている。