である。面積の96%が山で、耕地は猫の額ほどもない。かつては5月の雪解けと共に山を焼きジャガイモ・トウモロコシ・エゴマ
等を、7月にはソバを播いた。ソバは桧枝岐村にとって主要作物で、かつては9月には山の斜面がソバの花で白く染め上げられ
たというが、近年はその姿もなくなった。当然そばは日常食で、そばがきやそば団子として食された。有名なのは「裁ちそば」で
ある。小麦粉の入手難もあって「ソバ粉十割」なので、切れを防ぐために畳まずに重ねて、布を裁つように手前に引いて切るこ
とから命名された。昔は祝言の日に花嫁が「そば」を打つ習慣があった。生活を支える嫁の大切な心得の一つだったのである。
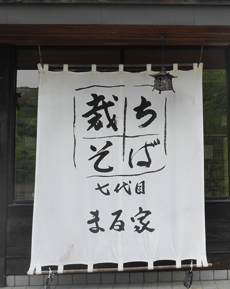



き七代目が裁ちそばを打つ。女将の山人
(ヤモード)料理が自慢。そば料理として
は、「裁ちそば・はっとう・つめっこ(すい
とん)」が定番である。旅館兼業のお店。
が、その昔村を訪れた役人が余りの美
味しさに驚き「普段の日に食べることを
禁じた」ため、法度→「はっとう」となった
という。「そば雑炊」も郷土料理の雄だ。
築し改築した。夢見亭の名は作家・村松
友視氏が著書「夢見そば」に因んで命名
した。店主・唐橋宏氏が昭和46年開業。
権現亭と共に育てた。全国亭に活動。
そば米は、そばの実を茹でた上で天日で乾燥させ皮を取り除いて作るのだが、その「そば米」を出汁で煮込んだものを「そば雑
炊」と言い、鶏肉やシイタケ・にんじん等とともに味を付け煮込んだものを「そば米汁」と呼ぶのである。徳島県では現在も幅広く
郷土食(家庭料理)として・・・学校給食でも・・・親しまれている。伝えるところによると、源平の合戦に敗れた平家の落ち武者が
祖谷地方に逃げ込み、お正月に米の代わりにそばを使って雑炊を作り都を偲んだことに始まると言われている。農水省の「全
国郷土料理百選」にも選ばれているが、昨年は東京オリンピックを睨んで同省の地域興し「食と農の景勝地」にも認定された。