開店した「三井越後屋(三越)」が天和3年(1683)「現金安売り掛け値なし」の新商法を引き札に託して十里四方に撒いたのが
最初だと言われている。その後、河竹黙阿弥・山東京伝・十返舎一九・式亭三馬等の作家、喜多川歌麿・葛飾北斎・歌川国芳等
の画家も数多くの引き札作品を残している。中でも平賀源内の「土用の丑年、うなぎの日。食すれば夏負けすることなし」(明和
6年・1769)のキャッチコピーは有名である。蕎麦の関係では、「開店案内」の引き札が目立つ。山東京伝の「手打生蕎麦「峯の
白雪」(神田「六花亭」)や式亭三馬の「手打新蕎麦即席料理」(芝増上寺「風詠庵」)などの長文の引き札が現在も残っている。
下段:平賀源内の肖像画

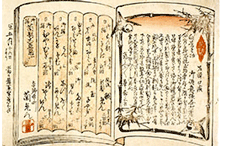


た。平成11年に現在の地で開店した。
ご夫婦で経営。花番を務める女将さんの
柔らかな接客が特に評判を呼んでいる。
日本酒の品ぞろえも豊富。夜来たい店。
32文」とある。引札や商品の袋、寄
席の半券等を集めた『懐溜諸屑)』所
収。下段:平賀源内。エレキテルの
発明で有名、博識多才な博物学者。
市川さん。十割の粗挽き、蕎麦がお客の
第一の狙い。蕎麦がきももっちりした食感
で人気を集めている。桧枝岐へ行く途中
に立ち寄る。本格派の蕎麦屋である、
接客や作業の際に、符牒の使用によって価格・品質・指示などを客に知られずにやり取りできる便利さもあるが、最近では公正
な取引を確保するために符牒などを使用しないように、例えば東京都中央卸売市場などでは指導を行っている。一般によく知
られている「あがり・おあいそ・ガリ・むらさき・・・」等は寿司屋の符丁だが、蕎麦屋にも独自の符丁がある。1杯を「つき」、2杯を
「まじり」、小盛りを「さくら」、大盛りを「きん」という。「天つき5杯のもり」といえば「天ぷらそば1に盛り4人前」のことであり、「もり
お代わり、台はさくらで」というと「盛りそばの小お代わり」になる。最近は耳にしなくなったが、江戸〜明治時代の名残りである。