三大うま味である昆布のグルタミン酸は池田菊苗(1908)、鰹節のイノシン酸は小玉新太郎(1913)、シイタケのグア
ニル酸は国中明(1957)が発見した。.いずれも日本人だ。我が国伝統の出汁文化が生んだ成果だといえよう。日本料理
は根底に出汁のうま味があるので食材の持ち味を邪魔するような味付けを嫌う。食材の癖や欠点を香辛料や濃厚なスープ
でカバーする西洋料理とは一線を画している。蕎麦の汁も「かえし」を出汁で割ることで味にコクが加わり深みを増す。
一流シェフは一生かけて「独自のスープ」を創り、一方日本の名料理人は「新しい食材を探す」といわれる由縁である。


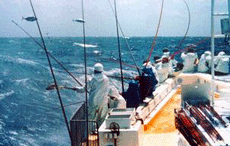

間にある戸建の蕎麦屋。清潔感漂う30
席の佇まい。お蕎麦は二八中心だが、
土日には黒姫の粗挽き十割が限定15
食という。11時・満席状態の繁盛店。
ぶ昆布ロードを走ったという。あの大
きな帆に夢を託したのだ。一方鰹は江
戸時代は近海漁業だったが、明治以降
次第に南洋へ範囲を広げていった。
した新進気鋭の蕎麦屋。河内鴨を使
った料理自慢のお店。蕎麦酒房とい
うだけに日本酒の品ぞろえは豊富で
ある。ご夫婦で経営する小体のお店。
占め、かつおは北緯40度〜南緯40度の太平洋が主漁獲地である。北海道と上方を繋いだのは北前船、往路で集荷し北海道
へ、復路は昆布やニシンを積んで京大坂へ。西回りなのは航路が比較的穏やかなのと、集荷する港が多かったためである。
大坂が昆布の集散地になり、江戸へは残り物が回されることになった。また比較的硬度の高い関東ローム層の水は昆布のう
ま味を引き出すのに適さなかったこともあり、江戸はかつお出汁が主流となったという。陸路交通の発達につれ東西の違い
が次第に縮小し、昆布と鰹の出汁を併用すると相乗効果のあることを国中明が発見したことで更に弾みがついたのである。