された「令義解」(天長10年・833)に「およそ市は肆(店)毎に漂(看板)を立て行名(販売品目)を題せよ」とあるのが初見なの
だという。江戸時代に入ると、庇の上に掲げる「屋根看板」、軒下に付ける「掛け看板・行灯」、店頭に置く「置き看板・行灯」等に
多様化した。さて蕎麦屋の看板だが、「守貞謾稿」(喜多川守貞著・1837〜1853)に元禄・享保時代に流行った看板の絵が載っ
ている(下の中央上の図)。三都はさておき東海道筋等地方の蕎麦屋の看板はこの様式が多かったようだ。蛇足ながら、現存
する世界最古の看板は古代トルコ(西海岸のエフェソスで発見された)の「売春宿を示す大理石に彫られた左の足跡」だそうだ。

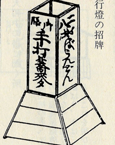
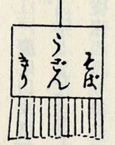
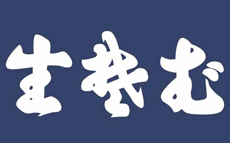

そばの伝統を守る正統派蕎麦屋だとい
われる。背広・ネクタイ姿の客も多く、商
談の場としても使われているようだ。銀座
にある静かなオアシス役を果たしている。
吊っていた看板。ひらひらは頭をぶつ
けないように付けたという。左は置き看
板で「招牌」とも呼ぶ。下段:「きそば」
と読む。よく見かける変体仮名である。
けの10席、ご主人が一人だけで切り盛
りする小体の店だ。そば粉は戸隠産。
喉越しの良いニ八そば。せいろ・やまか
け・おろしの三種を大中小盛りで選択。
体仮名が使われているためであろう。蕎麦屋の専売特許ではなく、てんぷら屋や寿司・甘味処にも見かけることが多い。古くは
平安時代の土佐日記(紀貫之)・枕草子(清少納言)・源氏物語(紫式部)等の仮名日記文学を生み、変体仮名が広く使用され
ていたが、明治33年(1990)の小学校令 施行規則改正によって学校教育では標準仮名文字に統一する方向が決まり、大正
12年(1922)に最終的に全廃されたのである。蕎麦屋等の看板に現在も変体仮名が使われるのは、「蕎麦」が日本の伝統食
であり、「由緒ある老舗」であることを示唆するためであろうか。今も名店「かんだやぶ」の末尾一文字「ぶ」は変体仮名である。