え、当時の風俗・習慣が機知と風刺で生き生きと描かれている。そばの専門書が極めて少ないなか、「柳多留」から得られる情報
は貴重である。例えば「新そばに小判を崩す一トさかり」(1765)・・そばの興隆と初物好きの江戸っ子の姿がよく描かれている。
「新見世のうちハ二八にわさびなり」(1783)・・「二八そば」の人気と山葵の台頭が窺われる。「せりふ切レたり延びたりで奢るそば」
(1827)・・台詞をとちった役者が関係者にそばを振舞う習慣「とちり蕎麦」があったことが分かる等はその一例である。「川柳」の呼
称は「柳多留」の選者・柄井川柳(1718〜1790)に因んだものだという。川柳もそばも江戸っ子気質の勃興と共に発展したようだ。

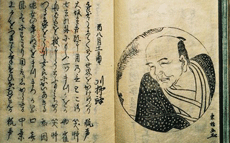
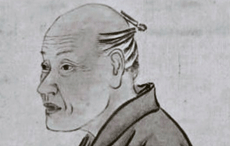

あって客足が途切れない。そば刺し・そ
ばがきに続いて締めに「そば切り」と続く
蕎麦の三連打のそば懐石であった。足
場が良いので小会合には最適である。
頑張っている。「冷やしすだち蕎麦」を頂
いたが、惜しみなくいれたすだちの輪切
りに感激。やや細切り、麺体の締まった
硬めの仕上がりは「堂源」譲りか。
(太田南畝)は江戸の三大狂歌師といわれる一方、本名は太田覃(ふかし)といい、れっきとした幕府御家人。登用試験に首席で合
格し、支配勘定方として大坂銅座、長崎奉行所に赴任するなど、二足の草鞋を履く才人であった。蕎麦への関心が高く、蕎麦の語
源・歴史・諸国蕎麦事情・江戸の蕎麦屋の盛衰などに詳しく、幾多の狂歌や小文を残している。「本山の蕎麦名物と誰も知る荷物を
おろし大根」の句は、江戸へ帰任する折に木曽・本山宿で詠んだもの.。「更科のそばはよけれど高稲荷森を眺めて二度とコンコ
ン」は名店「更科」を皮肉った作品である。「今までは他人が死ぬと思いしが俺が死ぬとはこいつあたまらん」が辞世の句であった。