蕎麦屋を開業するに到る道は次の3っである。1)家業の継承(老舗の場合) 2)蕎麦道場 3)有名店への弟子入り・・1) 2)
の場合も3)のステップを踏むことが多いようだ。狭い蕎麦屋の世界に濃密な人間関係が透けて見える。蕎麦打ち名人・高橋邦
弘氏は広島に「雪花山房・達磨」を開業しているが、営業よりも「教育・後進指導」に重点が置かれている。直接指導した弟子の
多くは各地で開業、孫弟子も全国に誕生しつつあり、高橋氏の影響下にある蕎麦屋の数は年々確実に増加の一途を辿ってい
る。氏の蕎麦打ち(二八)技術が「究極の完成品」と言われて久しいが、後進によってなお進化を続けて行くのであろうか。


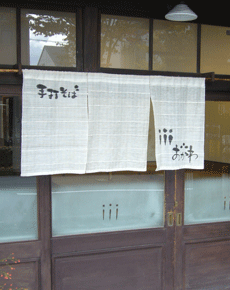
二八は緑色・細切り・硬いが艶のある蕎麦。出汁は辛目。ポタージュ系蕎麦湯。
元々は全て「手食」であったが料理に火を使うようになって箸が考えられた(紀元前15世紀・殷の時代)。匙・フォークが使われ
たのは14世紀になってからという。日本・中国・朝鮮・ベトナムは「箸文化圏」に属するが、中国・朝鮮は「匙主、箸従の共用文
化」」であるというのが正確なようだ。となると純粋な「箸文化」は日本だけと言うことになるのか?この用具の違いが各国の料
理メニュー・食器の形態や食礼(マナー)等の差を生んだ。箸を使う典型的なメニューに「麺」があり、麺が普及しているのは日本
を始めとして中国・朝鮮など「箸文化圏」に集中している。箸のみを使用する日本で蕎麦・うどん・そうめん等が格別に多食され
るのにも理由があるようだ。 (参考「食文化入門」石毛直道編)