を「三十石船」が毎日2便定期航行していた。上りが10時間、下り6時間かかったという。中間点の高槻・枚方辺りに差しかかる
と小船が寄って来て餅・汁・酒等を売りつけた。呼び声があまりに汚いので「くらわんか船」と呼ばれていたらしい。その中に伏
見の豪商・天王寺屋長右衛門の先祖にあたる越後浪人・只右衛門の「蕎麦切り船」があったと伝えられる。この古事は大阪・
北浜の蕎麦屋「三十石船」の箸袋に書かれていたとネットで読んだ。昨年早速北浜に同店を訪ねてみたが既に廃業のため実
物検証は出来ずに終わった。「蕎麦切り船」で当時使われた陶器の皿が今も川底から発見される。高槻の古曾部焼が多い。
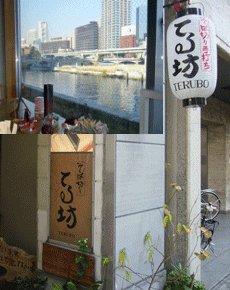


い眺望。店名はご主人の幼い頃の呼び
名とか。4代前まではこの地で料理屋を
やっていたとのこと。「玄びき」と「十割り」
を注文。前者は黒く歯ごたえがある。
鴨汁の注文が多い。「蔦屋」の屋号は
江戸時代の名店に因んだ命名と思わ
れる。「もり」と「手挽き」を注文する。
「手挽き」は透明感がある。
グラスの窓・照明・・・喫茶店を思わせる。
壁に片倉康雄氏の書と写真。八王子・車
屋の小川氏の弟子。片倉氏の孫弟子に
あたる。きびきびした動きをする奥さん。
蕎麦屋らしい筋は通っている。
だった。水量が多すぎるとべとついて「延し」の際に麺体を破ってしまう、少なすぎると「練り・延し」が難しく二進も三進も行かな
くなる。10年経った今でも梅雨時にはよく失敗する。水の入れすぎだ。指の感覚だけを頼りに3〜4回に分けて慎重に加水して
ゆくのだが最後になって間違える。梅雨時の蕎麦粉の保存も難しい。多湿・高温・光を避ける必要がある。製粉会社から送ら
れてきたシールドパック)を新聞紙で包み冷凍庫の奥深くにしまう。それでも一ヶ月が限度のように思われる。話が変わるが、
他に貯蔵が難しいものにワインがある。湿度・温度・光に加え振動に弱い。その繊細なところが蕎麦に似ていると思うのだが。