ことには恐らく異論は無いであろう。この時代は徳川政権確立・安定のために各地大名の参勤交代の制度化と国替えが頻繁に行われ
ていた。この二つが各地間の文化移転・交流に果たした役割は大きい。蕎麦に視点を置けば、信州各藩から各地への転封が目に付く。
蕎麦の全国への伝播に大きな役割を果たしたといえよう。高遠藩・保科正之が1636年出羽山形・1643年会津へ、松本藩・松平直政が
1638年出雲松江へ、上田藩・千石政明が1706年但馬出石へ転封されている。他にも、松代藩・松平忠昌の1618年越後高田・1624年越
前へ、飯田藩・京極氏が1600年、飯山藩・青山氏が1717年に丹後へ入封。信州から各地へ蕎麦は見事に拡散していったのである。


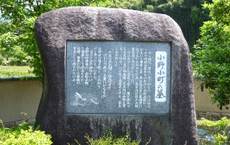

公園の管理も引き受ける面白い存在。小
野小町の墓と歌碑がある。部屋より一望。
蕎麦は鄙には稀な繊細なセンス。拓朗亭
(亀岡)で修行したという。
雪が多い。丹後市で老舗「よ志のや」の当主
と女将が引退後新築した蕎麦屋。囲炉裏が
切られ広々した設計。店名は故城山三郎氏
から贈られた色紙「天風朗々」から。(裏店内)
るという。小町の終焉の地とされる。「しの
ぶれど色に出にけり・・・」の歌碑もある。
下段は歌仙の「蕎麦おはぎ」 、蕎麦なら
ぬおはぎでそば前を楽しむ。これも風流。
であったらしい。ところが蕎麦屋は「生の酒」を供していたため、”蕎麦屋で飲む酒は美味い”の巷説が広がったようである。蕎麦屋で酒
を飲む風俗は、客が”簡単なつまみと酒”で蕎麦が打ち上がるまでの時間をつぶしたことに始まるとされている。酒が「蕎麦前」と呼ばれ
るようになった由縁である。風呂帰りにつまみで酒を少々、盛り蕎麦で締めてサッと席を立つ、これが当時の江戸っ子の気性に合った
のであろう。現在も関西はともかく、東京では「蕎麦と日本酒」は表裏一体のものでしょう。昼間に飲む蕎麦屋酒は格別。江戸の文化を
懐かしむ日本人の遺伝子が密かに目を覚ます瞬間かもしれない。昼間酒を飲んでも遠慮の要らない雰囲気が蕎麦屋には必要なのだ。