ろう。細長く切られた麺である共通項はあるが、まず原料がまったく違う(小麦粉とソバ粉)だけでなく、作り方(手打ちと足踏み)、
顧客層、業界のあり方まで異なっている。「蕎麦屋に子供」、「うどんに酒」は似つかわしいとはいえないだろう。蕎麦屋は自家製粉
・栽培に手を伸ばすところも珍しくないが、うどん業界は大手製粉会社と製麺所があり、「玉買い・再茹」で営業するうどん屋も多く
、蕎麦屋の自己完結志向に比べると分業体制が強いと言える。粉に対する拘りも違いが顕著だ。蕎麦が国内産に拘るが、うどん
はASW(オーストラリア産)が主流だ。蕎麦は趣味食化を強め、うどんは一般食化が進む、食への基本姿勢の違いが根本にある。

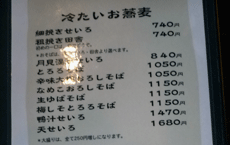



「みたに」へ。店主は芦屋の「土山人」で
修行,7年前に開業した。品書きは「せいろ
・田舎・太切り」から選ぶことが出来る。
「田舎・せいろ」の二種盛り(九一)を食す。
価な「せいろ」で740円。他は4桁の数字
が並ぶ。下段は高松「さか枝」のざるうど
ん。価格はなんと180円。せいろ蕎麦の
三分の一。商品政策の違いが明らか。
昼食時とはいえ店内は長蛇の列が出来
ている。セルフサービス・・・うどんの玉は
大・中・小から選び、トッピング(一個80円)
も自由に選べる。蕎麦屋とは違う雰囲気。
ィー化したもので、当時の江戸の「蕎麦とうどん」の関係が垣間見えて面白い。源そばこ(頼光)が薬味の四天王(渡辺のちんぴ、
坂田の唐辛子、卜部のかつお、碓井大根)を引き連れて、うどん童子(酒吞童子)を見事退治する様を面白おかしく描いている。
うどんが主流だった江戸初期(16世紀)から次第に蕎麦が普及して17世紀半ば頃には江戸っ子の嗜好が、「うどんから蕎麦」へ
急速に移行していったことが、この黄表紙から推察できる。江戸に政治の中心が移ったとはいえ、文化・・とりわけ食文化は依然
として上方の影響下にあったので、江戸っ子の上方コンプレックスは相当なもの? この黄表紙で溜飲を下げていたのであろう。