蕎麦復興の旗手となった。彼の蕎麦打ち技術を学ぼうと全国から足利に殺到した(「足利詣」)のは現在も語り草である。「片倉康雄
手打そばの技術」は名著として現在も蕎麦屋を志す職人の必読書である。新島繁(別記)は蕎麦文化史の第一人者。「氏原暉男」
(1934〜2013)、信州大名誉教授。信州大ソバ・高嶺ルビー等の育種に専心。退官後はNPO「麻薬撲滅協会」を設立し、ミャンマー
でケシの代替作物としてソバ普及活動に貢献する。「高橋邦弘」(1944〜)、片倉康雄の一番弟子。愛車の「達磨号」を駆って全国
の蕎麦普及・啓蒙・町興しに奔走する。現役蕎麦打ち名人の呼び声が高い。番外に「日新舎友蕎子」(別記)を入れねばなるまい。
高橋邦弘氏
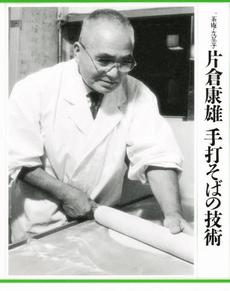
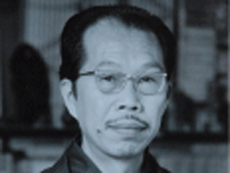



りの入り口は総本山に相応しい威容だ。
(裏)は片倉康雄著「手打ちそばの技術」
いまも名著として蕎麦屋を志す職人達の
バイブルとなっている。
上段裏は、新島繁の著書「蕎麦史考」と
日新舎友蕎子著「蕎麦全書」。
高橋氏の幼年期のあだ名に由来する。
氏も古希を迎え、来年は大分県杵築市の
山中に移るという。東京〜八ヶ岳〜広島
〜大分・・・此れが終の棲家となるのか。
蕎麦事情を現在に伝える唯一の書籍である。蕎麦全書が平成18年、新島繁校注・藤村和夫訳解による現代語版が出版され、はじ
めて一般の目に触れるようになった。新島繁(1920〜2001)は昭和23年に蕎麦屋「郷土そば さらしな」を開業したが、実務は他に
任せもっぱら蕎麦文化史の研究に専念、昭和45年には「日本麺食史研究所」を設立した。蕎麦は大衆食であったので残された文
献も少なく、新島は日記・紀行文等の断片的に書かれた古文書を丹念に掘り起こし整理する、地味で基本的な仕事をやり遂げた
「蕎麦文化史」のパイオニアである。著書に「蕎麦史考」「蕎麦辞典」「近世蕎麦随筆集成」「蕎麦歳時記」「蕎麦今昔物語」がある。