
郷土蕎麦の物語⑤
木曽路はそばの歴史街道です
「木曽路はすべて山の中である」 島崎藤村「夜明け前」の冒頭フレーズです。
京と江戸をつなぐ中山道の三十三番・贅川宿から南へ向かって四十三番・馬籠宿までの十一宿を木曽路と呼びますが、三十二番・本山宿を含めると「そばの初・・」が勢揃い。木曽路はそばの歴史街道でもあるのです。
 本山宿には「そば切り発祥の地」(注1・写真)の木碑が立ち、上松宿には「現存する日本で2番目に古い蕎麦屋・越前屋(元禄元年・1624年創業)」(注2)が、三十九番・須原宿には、「そば切りの名が出てくる最初の古文書」(注3)が発見された臨済宗・定勝寺があります。伝承も含めこれだけ「そばの初・・」が多いところは全国どこにも見当たりません。木曽路(中山道)がそば切りの発祥・伝播に大きな役割を果たしたことは疑いのないところです。
本山宿には「そば切り発祥の地」(注1・写真)の木碑が立ち、上松宿には「現存する日本で2番目に古い蕎麦屋・越前屋(元禄元年・1624年創業)」(注2)が、三十九番・須原宿には、「そば切りの名が出てくる最初の古文書」(注3)が発見された臨済宗・定勝寺があります。伝承も含めこれだけ「そばの初・・」が多いところは全国どこにも見当たりません。木曽路(中山道)がそば切りの発祥・伝播に大きな役割を果たしたことは疑いのないところです。
信濃の中でも一番美味で有名なのが「霧下そば」です。
「霧下」は地名ではなく、越後(新潟県)と信濃(長野県)の県境辺りの標高500~700mで、昼夜の気温差が激しく朝霧が発生しやすい中山間地で穫れるそば粉(注4)がことのほか美味しいところから、霧下そばと呼ばれるようになったのです。天岩戸の伝説で有名な戸隠山・戸隠神社のある旧戸隠村(現長野市戸隠)はその中心になります。
霧下そばの美味さの秘密について信州大学の井上直人名誉教授(農学部)は「ソバには、雨だけでなく霧や露を葉の表面から直接取り込む高い能力があったのだ。・・・日本の山里では、夜温が下がるだけでなく湿った涼風が山から下ってくるので、夜露は葉にたまり水分がどんどん補給される。「霧下そば」がよいと言われたのは、霧が出るような水ストレスが小さい環境がソバ栽培に適すると言っていると理解できる」と指摘しています。
古来山岳信仰で栄えた戸隠には、修験者が多く集まってきて、その携行食としてそばが入ってきたと伝えられています。申し上げるまでもなく当初はそば切りではなく「そばがき」「そば団子・餅」の類でした。
戸隠そば(そば切り)の特徴は、甘皮(外皮)、場合によっては玄そばごと挽くいわゆる「挽きぐるみ」で、茹でた後も水切りをせず(美味しい水も一緒に味わってもらうため)に、「ボッチ盛り」という一口で食べられるよう馬蹄形に小分けして盛り付けることです。薬味には地元の伝統野菜・戸隠大根と呼ばれる辛味大根が使われることも付け加えておきましょう。
「霧下そば」で忘れることが出来ないのが小林一茶生誕の地である柏原です。
柏原は長野県の北部にあり、信濃富士とも呼ばれる黒姫山(標高2053m)の麓にあって標高700~800mの中山間地ですが、火山灰地の地質であるため畑が多く良質のソバ粉が産出され、戸隠に連なるそば処として知られています。特に柏原地域では「凍りそば」(注4)が江戸時代からの名産品でした。
明治時代には柏原の名物として幅広く販売されていたといいます。現在では柏原地区にだけ残っている貴重なそばです。
一茶は14歳で江戸へ奉公にでて、故郷・柏原へ戻ったのは50歳の時でした。 「そば所と人はいふ也赤蜻蛉」 一茶
一面に咲き誇る白いそば花の上を赤蜻蛉がすいすい飛ぶさまを詠んだ句ですが、柏原の清々しい空気の中に白と赤のコントラストが目に浮かぶようです。
現在も蕎麦屋数十軒がその美味さを競っています。島根の出雲大社、東京の深大寺、福井の永平寺等と並ぶ一大門前そばは一見の価値がありそうです。
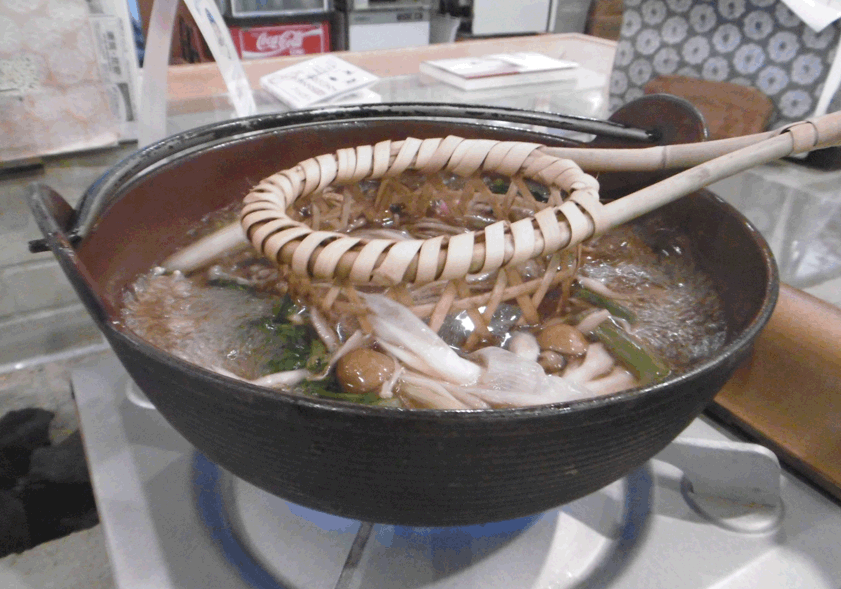 その他にも、オヤマボクチをつなぎに使う「富倉そば」、カブ菜を乳酸菌発酵させた漬物と合わせる開田村名物の「スンキそば」、小さな籠に入れた季節の野菜と一緒に鍋で湯がいて食べる奈川村の「投汁そば」(写真)、茹でた千切り大根に水溶きしたそば粉を絡めて食べる栄村の「早そば」等々です。
その他にも、オヤマボクチをつなぎに使う「富倉そば」、カブ菜を乳酸菌発酵させた漬物と合わせる開田村名物の「スンキそば」、小さな籠に入れた季節の野菜と一緒に鍋で湯がいて食べる奈川村の「投汁そば」(写真)、茹でた千切り大根に水溶きしたそば粉を絡めて食べる栄村の「早そば」等々です。
このように信州には至る所にそば処があると言っても決して過言ではありません。それは信州にはそば栽培に適した自然環境が揃っていたからです。
山地面積は北海道に次いで全国第2位、中山間地集落数・世帯数でいずれも全国第1位を占めるだけでなく、年間平均気温が12度(全国第5位)という、ソバ栽培に最適の冷涼地でもあるのです。
「梁越そばまんじゅう」はソバの産地で有名な長野県南佐久郡川上村の郷土食で、熱い灰の中で焼いた蕎麦餅のことなのですが、お椀に入れた蕎麦掻きにそば粉と生姜、葱、味噌を混ぜて団子状にして、天井の梁を越すほど高く放り上げ、落ちてくるのを椀で受け止めるのを繰り返し(空中に放り上げることで饅頭の中に適当に空気が混るので硬くならないのだといいます)、それを炉端の灰で焼き、甘味噌やゴマ醤油をつけて食べるのが習わしでした。「草鞋穿で焚火に温りながら、その「ハリコシ」を食い食い話すというのが、この辺での炉辺の楽しい光景なのだ」と藤村は書いています。信州の山村ではそばは昔からこのように身近な日常食(ケの食)だったのです。現代人が忘れてしまった、なんとも懐かしい人間の温もりを感じる良い話ではないでしょうか。
(注1)「そば切り発祥の地」の伝承 芭蕉十哲の一人・森川許六は「本朝文選」の中で「そば切りといえば、もと信濃国本山宿から出て、あまねく国々にもてはやされける」と紹介しています。
(注2)「越前屋」 十辺舎一九の「木曽街道膝栗毛」(1822)に紹介されたほか、太田南畝(蜀山人)の狂歌や喜多川歌麿の絵などがあります。
(注3)「そば切りの初見」 「そば切り」の文字が初めて現れたのが、定勝寺住職が書いた日記「番匠作事日記」で、本堂改修工事完成を祝う奉納品一覧の中に「振舞いソハキリ 金永」(1574)と記録されています。