え文化を育んで来た。茶道・生花・染物等の伝統文化をはじめ、豆腐・湯葉・麩・京野菜に至るまで広くこの水の恩恵に浴してい
る。名声高い京料理も旨みのある「出汁」があってのことだ。ミネラル量の低い京都の水には昆布の旨み(グルタミン酸)が失わ
れずに保たれる。北海道の昆布と京都の水を繋ぐ仲人役を北前船が果たした。さて蕎麦だが、打ちあがった蕎麦の成分の約三
分の二は水である。純度の高い水が求められるのは当然のことで、求道的蕎麦屋の中には水を求めて転地、自ら井戸を掘る人
も現れる。言うまでもなく蕎麦出汁のうまみも昆布が主役を務めている。が、京都の水盆も近年減衰の傾向を強めているという。


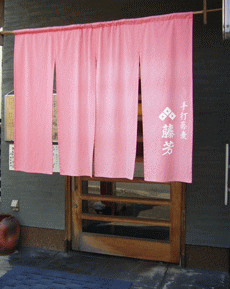
い佇まいの店。店内には趣味で集めたと
いうアンティークが飾られる。秀吉愛用の
「豊国水」と同水系に井戸を掘り使用して
いる。珍しく韃靼そばがある。
小振りのお店。女性客を意識した「甘味」
もある。蕎麦は白くさっぱりとした出来。二
八か。
母親が経営する。北海道・恵庭産粉、生
粉打ち、黒く短くやや太めでやや柔らか
い。行燈風の照明が和風を演出している。
れていない。季節が全く逆になることを利用した面白い事例であった。最近ではスペインのカンタブリア州で信州蕎麦の栽培が行
われるようになったと聞く。日西文化交流事業「一つの花フェスティバル」で山崎良弘氏と第十代名人・赤羽章司氏が蕎麦打ちの
妙技を披露したことが縁となって州政府の肝いりで蕎麦栽培が進められるようになったのである。栽培地がSoba村という名である
ことも面白い。ところで「蕎麦切り」の方の海外進出も昨今目を見張るものがある。ネットで検索してみると世界の代表的な都市の
殆どに蕎麦屋が進出している。日本の固有の伝統食文化が世界各地の人に理解される日が来ることは歓迎すべきことであろう。